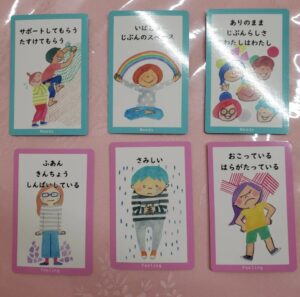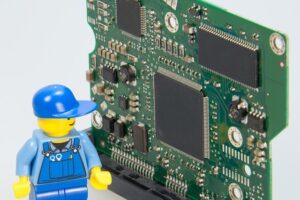25年12月19日 長岡和光幼稚園なごみ保育園の先生方の研修会
長岡和光幼稚園なごみ保育園の先生方の研修会に参加させていただき、現場の先生方から学ばせていただきました。今回、講師は若槻園長で、私は僭越なオブザーバーとして、最後の感想をお話させていただきました。園児の指導法などについて […]
25年4月24日 子どもニーズガード
相談室では言葉にできない子どもの気持ちをカードを使って視覚的にサポートをしながら引き出しています。そして、どうしたい、どうなりたい、どうしてほしいというニーズも引き出します。ニーズの場面では涙する子どもも多いです。言語化 […]
マーケティング~テーマ提案~研究・開発~製品化までの流れ 研究開発9
エンジニアのあなた、あなたが進めている研究開発テーマはどのように提案されるのでしょうか?また、それはどのように製品化されるのでしょうか?この記事では、①要素技術に至るまでのテーマ起案の流れ、②要素技術~機能開発~量産化開発までの流れ、③量産化後のステップについてお話したいと思います。
派遣エンジニアを活用してソフトウエアを開発しよう メリットとデメリット 研究開発8
組込みシステムやその他ソフトウエアを外注さんにお願いする場合、派遣エンジニアさんにお願いする場合がありますね。この記事では、派遣エンジニアさんにお願いする場合のメリットとデメリットについてお話します。今後、外注さん、派遣エンジニアさんへ依頼を考えるうえでの助けになれば幸いです。
外注さんを活用して組込みシステム用ソフトウエアを効率的に開発しよう 研究開発7
初めて組込みシステム用ソフトウエアをしようと思っているあなた!でも、あなたも貴方のチームのメンバーも開発経験がありません。困りました。この記事では、組込みシステムとは関係のない技術者が、初めて組込みシステム用ソフトウエアを開発するときの仕事の進め方についてお話したいと思います。
思いついたアイデアは権利化しよう。時間を手間をかけずに、特許を書こう! 研究開発4
要素技術研究の成果として得られたアイデア(発明)も、競合退社が先行して特許を出してしまうと開発計画の見直しや、事業方針まで見直すことになりますね。この記事では、あなたのをアイデアを1日でも早く権利化(特許化)するための方法について、私の経験からお話したいと思います。
独自開発する?いやいや、オープンイノベーションで進めましょう。研究開発3
あなたの会社に新しい技術を導入する場合、自社で研究開発を進める場合と、社外から技術を導入する場合があると思います。この記事は、社外から新技術を導入する方法の一つであるオープンイノベーション、特に大学からの技術導入の流れについてお話したいと思います。
その要素技術研究を自分でやるの、それとも、オープン・イノベーションでやるの!? 研究開発2
自社で基礎研究(要素技術研究)を行わなくても、①社外で技術を開発させる、②社外から技術を導入する等、すべて自社で行うことはないですよ!この記事では、自社で基礎研究(要素技術研究)を行うべきもの、社外から技術を導入するオープンイノベーションで進めるべきもの、を決めるポイントをお話したいと思います。
要素技術研究(基礎研究)と製品開発(応用研究)の違いは何? 研究開発1
一般に基礎研究とは、”自然またはその他の現象をより良く理解または予測するための科学的理論を向上させることを目指した科学研究(Wikipedia)”と、定義されてます。しかし、我々企業人がいうところの基礎研究は、ちょっと違います。この記事では、企業の基礎研究(要素技術研究)と製品開発の定義についてお話したいと思います。