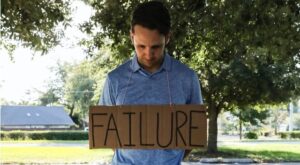昇格試験の合格のための9個の評価ポイント 昇格試験:第32回
昇格試験は、職位基準書に基づいて受験する職位に相当するかチェックするための試験です。この記事では、チェックされる9個の評価ポイント(課題設定能力、課題解決能力、専門性、協調性、洞察力、リーダシップ、コミュニケーション能力、成長性、指導力)についてお話したいと思います。
昇級試験に合格しやすい組織(業務形態)とそうでない組織(業務形態) 昇格試験:第31回
技術者のあなたが、所属する組織や職種によって、昇格試験の合格率は大きく変わります。これはあなたの責任ではありません。この記事では、どのような組織・職種が合格率が高く、一方でどのような組織・職種が合格率が低くなるのかお話します。また合格率が低い組織・職種の場合、どのようにすれば合格に近づけるのかお話しております。
昇格試験の2つの弊害 (マネージャさんの個人的な見解)昇格試験:第30回
昇格試験は、① 上司の好き嫌いによる評価を防ぐ、②部門による人事評価の偏りを防ぐ、③昇格する人数を管理するなどの役割がありますね。一方で、昇格試験の仕組みの弊害もあります。この記事では、昇格試験の2つの弊害について、私の個人的な見解についてお話したいと思います。
会社が全社共通の昇格試験を実施する3つの狙い(目的)は何だろう? 昇格試験:第29回
毎年、同じ時期に、同じような内容(成果論文、課題論文、プレゼン、グループディスカッション等)で実施される昇格試験。会社はなぜ昇格試験を実施するのでしょうか?昇格試験など実施しなくても、上司の判断で昇格を決めれば?と思いませんか?この記事では、あなたの会社が昇給試験を実施する理由についてお話したいと思います。
上司から見て、成果論文の指導に困る人 昇格試験:第28回
あなたの上司も人の子です。あなたの上司も忙しいです。その合間を縫ってあなたの成果論文をチェックします。この記事は、上司の視点から成果論文を修正するときに困った人(指示していることを聞かない人、指示していることが理解できない人についてお話したいと思います。
これからの管理職試験 課題論文と成果論文の違い!課題論文の書き方! 昇格試験:第27回
この記事では、管理職(課長職)試験にて問われる課題論文についてお話します。具体的には、①課題論文執筆・グループディスカッションのスケジュール、②成果論文と課題論文の違い、③成果論文の完成度が上がってから課題論文に取り組むこと!、④課題論文を執筆するために準備すること!、⑤5 課題論文の書き方についてお話ております。
来年、昇格試験に合格するためにやるべき3つのこと 昇格試験:第26回
1年後に昇格試験を受験したいと思っている方、今から試験に向けて準備をしましょう。この記事では、受験1年前に事前にやって3つのおくべきこと、1)職位基準書を熟読しておくこと、2)文書を書く癖をつける(成果論文の執筆の練習)、3)聞き手を意識したプレゼンテーションについてお話したいと思います。
これからの管理職試験 成果論文のプレゼンテーションの準備と練習 昇格試験:第25回
やっと成果論文の執筆・提出も終わりました。お疲れさまでした。やっと一息!・・・違いますね!もうひと頑張り! 次に、成果論文を説明するためのプレゼンテーションの準備を始めましょう。この記事では、プレゼンテーションの準備・練習について、お話したいと思います。
昇格試験に失敗した方へ。来年に向けてやっておいた方がいい3つのこと 昇格試験:第24回
今年の昇格試験はいかがでしたでしょうか?残念ながら不合格だった方で、来年度も挑戦したいと思っている人にアドバイス(①業務目標の設定時に成果論文の課題を意識してまとめること、②普段の業務の中のアイデアや工夫を成果論文の創意工夫としてまとめること、③課題設定の重要性等)をお話したいと思います。
これからの管理職試験 成果論文を早速執筆しましょう。 昇格試験:第23回
この記事では、管理職(課長職)試験で執筆が求められる成果論文(昨年度の業務成果をまとめたもの)の書き方を、①部門方針(中期計画)の説明、②部門方針(中期計画)を達成するための課題、③部門方針(中期計画)等の課題を解決するためにあなたが取り組むべき課題、④課題を解決するための創意工夫、⑤今後の展開の順でお話します。