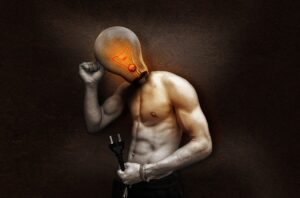50歳からの転職は異業種へ!専門性は活かしながら前職の人脈を活かそう 転職:第24回
12/10/2021
50歳を過ぎたおじさんの場合、私のお勧めは、①異なる業界へ転職(前職の人脈の可能性、円満退社につながる)、②同じ職種へ転職(即戦力として求められるのは今までの経験です)と思います。この記事では、①、②の理由について、私の転職経験からお話したいと思います。
社会人大学院博士課程の入学から修了までの3年間の私の過ごし方 社会人大学院6
10/10/2021
社会人から大学院博士課程を目指しているあなた、社会時大学院の3年間は長いようで案外短いものですよ。この記事では、社会人の方が社会人博士課程に入学した後の3年間の過ごし方について、私の経験からお話したいと思います。今から社会人博士課程を目指しているあなたの助けになれば幸いです。
外注さんを活用して組込みシステム用ソフトウエアを効率的に開発しよう 研究開発7
09/10/2021
初めて組込みシステム用ソフトウエアをしようと思っているあなた!でも、あなたも貴方のチームのメンバーも開発経験がありません。困りました。この記事では、組込みシステムとは関係のない技術者が、初めて組込みシステム用ソフトウエアを開発するときの仕事の進め方についてお話したいと思います。
50歳からの転職で、戸惑ったこと、困ったこと、違和感を感じること。 転職:第23回
06/10/2021
50歳を過ぎて転職を考えているあなた、50歳を過ぎてからの転職には、転職後に戸惑いや困ったことがついてきます。この記事では、私が転職した後に感じた戸惑いについてお話しております。今は、この戸惑いは楽しみの一つになっております。転職を考えている方についてご参考になれば幸いです。
会社が全社共通の昇格試験を実施する3つの狙い(目的)は何だろう? 昇格試験:第29回
03/10/2021
毎年、同じ時期に、同じような内容(成果論文、課題論文、プレゼン、グループディスカッション等)で実施される昇格試験。会社はなぜ昇格試験を実施するのでしょうか?昇格試験など実施しなくても、上司の判断で昇格を決めれば?と思いませんか?この記事では、あなたの会社が昇給試験を実施する理由についてお話したいと思います。